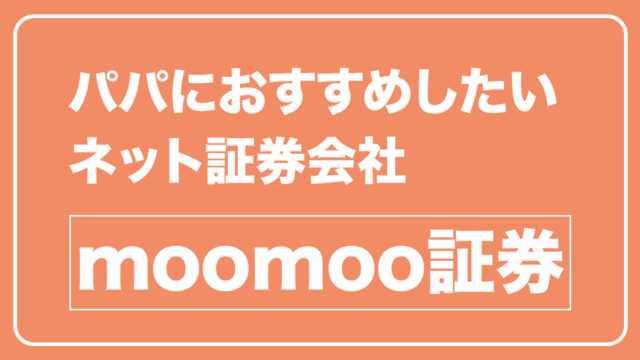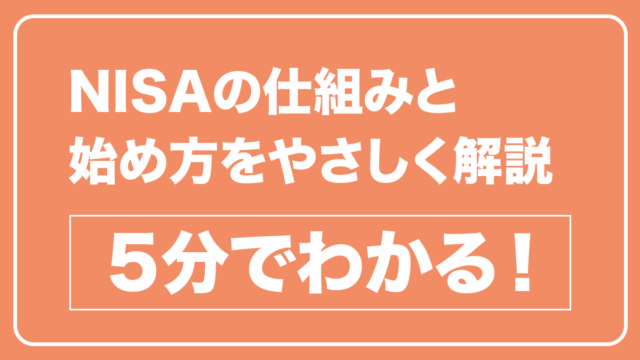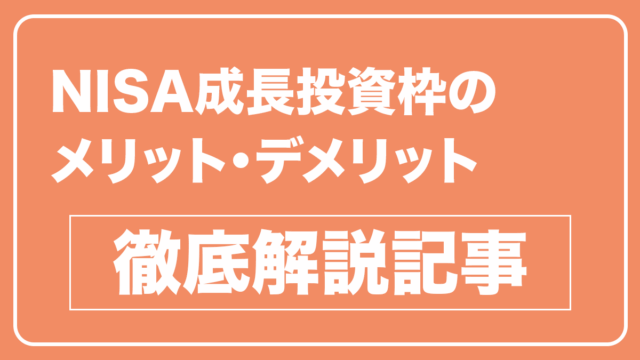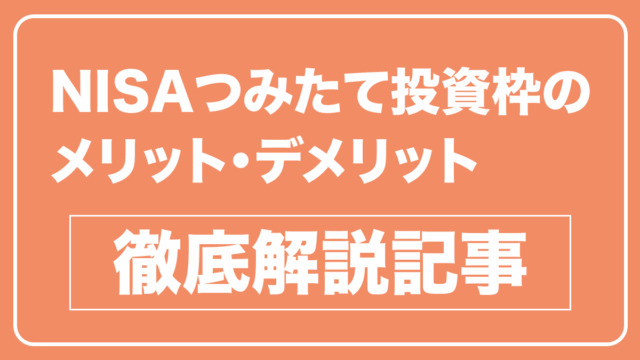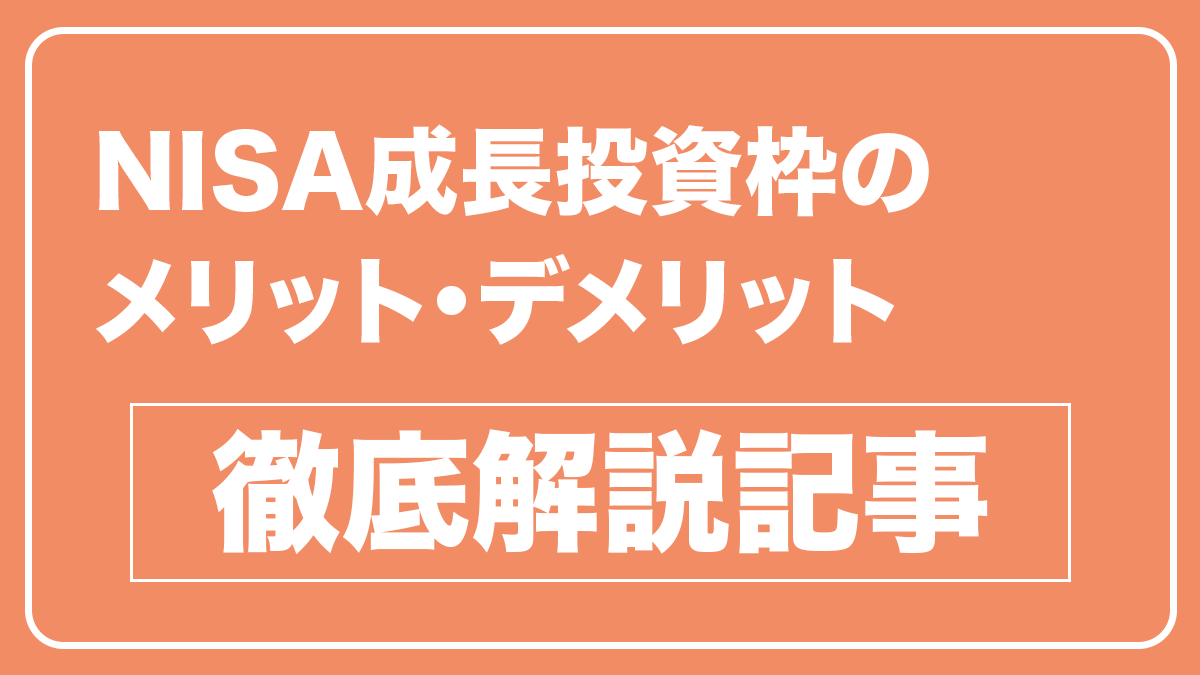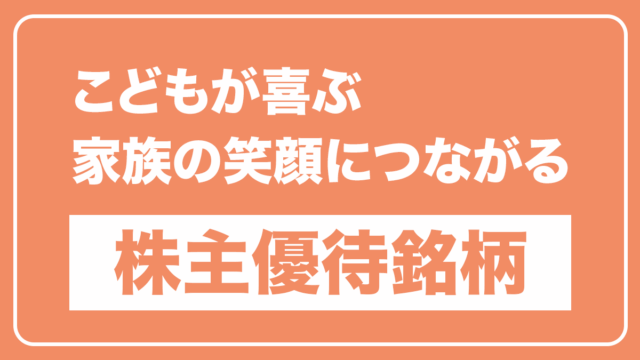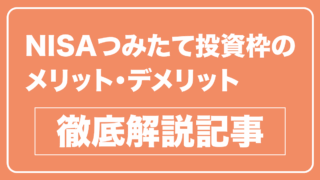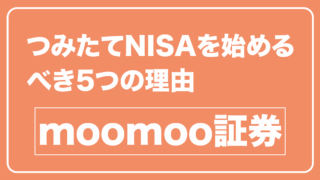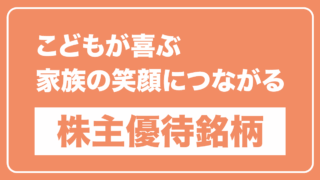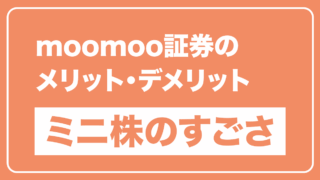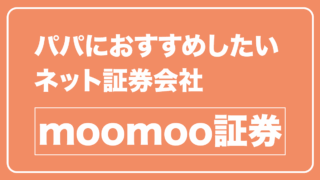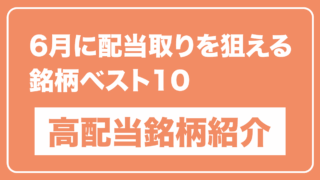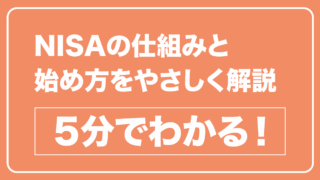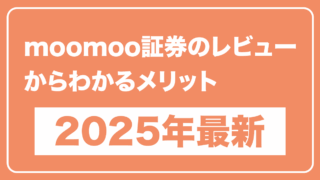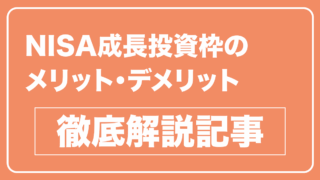収入はあるけど貯金は増えないんだよな…
ちなみにNISAはやっているかい?
NISAってつみたて投資のやつ?
今日紹介するのはNISAの成長投資枠だよ
そんな不安を抱える子育てパパに知ってほしいのが「NISAの成長投資枠」
最近よく聞くNISAには、つみたて枠だけでなく「成長投資枠」という選択肢もあります。
この記事では、成長投資枠のしくみから、メリット・デメリットまでを中学生でもわかる言葉で徹底解説。
忙しい地方のパパでもムリなく資産形成を始められるように、具体的な例や会話も交えて紹介します。
NISAの成長投資枠とは?
NISA(ニーサ)は、投資で得た利益が非課税になる制度です。
2024年から始まった新NISAでは、 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの非課税枠が用意されています。
つみたて枠は聞いたことあるけど、成長投資枠って何が違うの?
成長枠はもっと自由に銘柄を選べるんだ。個別株も買えるから、大きく増やしたい人におすすめだよ
自分で選ぶってこと?なんだか難しそう…
最初は難しく感じるかもしれないけど、ETFとか分散されてる商品から始めれば安心だよ
成長投資枠とは、個別株式やETFなど、より高いリターンが期待できる商品に投資できる枠です。
年間の非課税投資枠は240万円。つみたて枠と合わせて最大360万円まで非課税で投資できます。
- 年間投資上限:240万円(毎月最大20万円)
- 投資対象:上場株式、ETF、REIT、特定の投資信託
- 投資スタイル:自分で商品を選ぶアクティブ型
NISAの成長投資枠のメリット
NISAはつみたて枠が一番いいじゃないの?
実は、つみたて枠と同じぐらいすごいんだよ
メリット1:自分で銘柄を選べる自由度
成長投資枠の大きな魅力は、投資する商品を自分で選べる点です。
たとえば、自分の好きな企業の株や、話題の業界に関連するETFなど、 関心のある分野に投資できるため、投資へのモチベーションも上がります。
業績が伸びている企業にうまく投資できれば、 数年で大きなリターンが得られる可能性もあります。
たとえば、好きなゲーム会社の株とかも買えるの?
もちろん!好きな会社に投資するのって、楽しいし応援にもなるんだよ
メリット2:高いリターンを狙える可能性
つみたて枠が安定重視なのに対し、成長投資枠は「攻めの投資」ができる枠です。
うまくいけば、つみたて枠よりも良いリターンが得られることもあります。
もちろんリスクもありますが、 「収入を増やしたい」「将来の教育費に備えたい」パパには有効な手段です。
年利別シミュレーション(5年後)投資額100万円した場合
| 年利 | 5年後の資産 |
|---|---|
| 3% | 約116万円 |
| 7% | 約140万円 |
| 10% | 約161万円 |
メリット3:配当金も非課税になる
成長投資枠では、株式投資によって得られる「配当金」も非課税となります。
高配当銘柄投資を目指す方には特にオススメです。
通常、配当金には約20%の税金がかかりますが、NISA内であればすべて非課税です。
たとえば、年間配当利回りが3%の株を100万円分持ってる場合。
本来は3万円のうち6,000円が税金で引かれますが、NISAならそのまま3万円を受け取れます。
これは、毎月の家計を補う「プチ収入」としても魅力です。
NISAの成長投資枠のデメリット
成長投資枠、メリットしかないじゃん!
もちろんメリットが多いけど、デメリットも確認しよう
デメリット1:損益通算・繰越控除ができない
投資って、うまくいかなかったらどうなるの?
NISAでは損しても他の利益と相殺できないんだ。でも、そもそも非課税だから仕方ない部分もあるね
NISA口座で損失が出ても、他の利益と相殺する「損益通算」ができません。
たとえば、通常の証券口座なら、利益と損失を合わせて税金を調整できますが、 NISAは非課税の代わりにその調整ができません。
また、損失を翌年以降に繰り越して使う「繰越控除」も使えません。
つまり、利益が出ればすべて非課税ですが、損した分はなかったことになる仕組みです。
損益通算とは、「もうけ(利益)」と「損(損失)」を合計して、税金を調整するしくみのことです。
たとえば、ある年に株で10万円の利益が出たけど、別の株で5万円の損をしたとします。
この場合、10万円 – 5万円 = 5万円の利益として計算され、税金もその5万円に対してかかることになります。
しかし、NISAでは利益が非課税になる代わりに、損が出てもそれを他の利益と合算して税金を調整することができません。
つまり、NISA口座で損をしても、それを使って節税することはできないということです。
利益と損失を合わせて税金を調整できますが、 NISAは非課税の代わりにその調整ができません。
また、損失を翌年以降に繰り越して使う「繰越控除」も使えません。
つまり、利益が出ればすべて非課税ですが、損した分はなかったことになる仕組みです。
デメリット2:銘柄選びに知識と判断が必要
どの株を買えばいいのかさっぱりだよ…
最初はETFから始めるのが安心かな。徐々に慣れていけば大丈夫!
成長投資枠では、自分で投資先を決める必要があります。
これは自由である反面、銘柄選びに失敗すると損失を出すリスクも。
特に初心者は「話題だから」「なんとなく」で選んでしまいがちですが、 業績や配当、将来性をしっかり調べる力が求められます。
不安な場合は、ETFやインデックスファンドから始めるのも一つの手段です。
まとめ:攻めと守りを使い分ける投資戦略を
NISAの成長投資枠は、積極的に資産を増やしたいパパにとって、 大きな可能性を秘めた選択肢です。
リスクもありますが、制度を正しく理解し、自分に合った方法で活用すれば、 家計に余裕と未来の安心をもたらしてくれます。
「つみたて枠=守り」「成長枠=攻め」
この両方をうまく使いこなすことで、 投資初心者でも一歩先を行く家計戦略が実現できます。