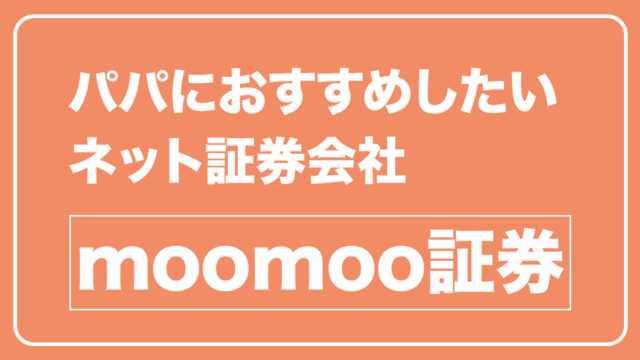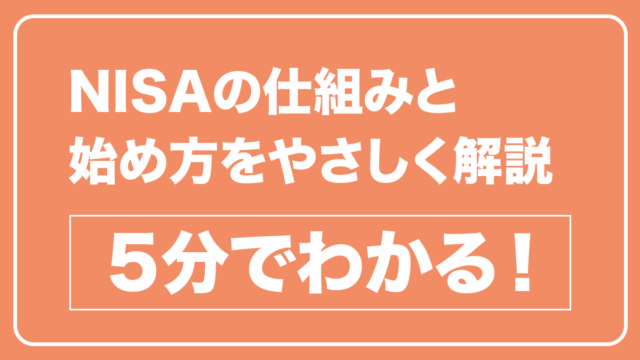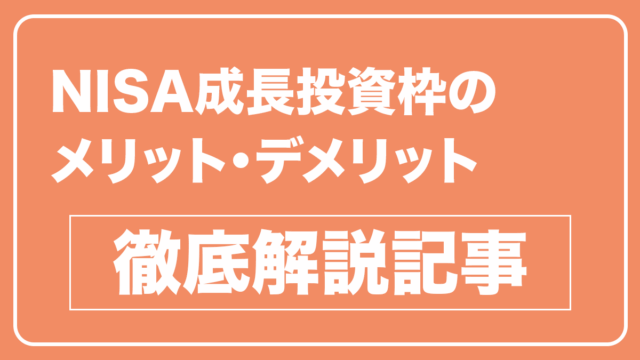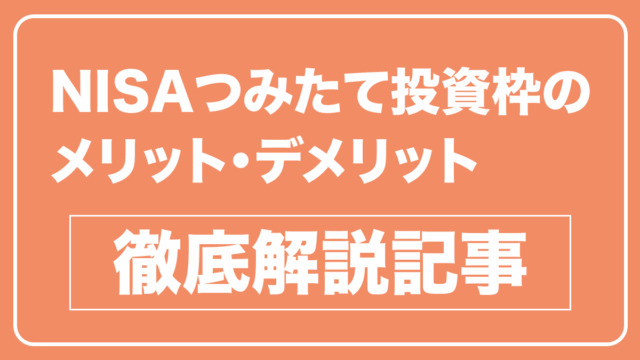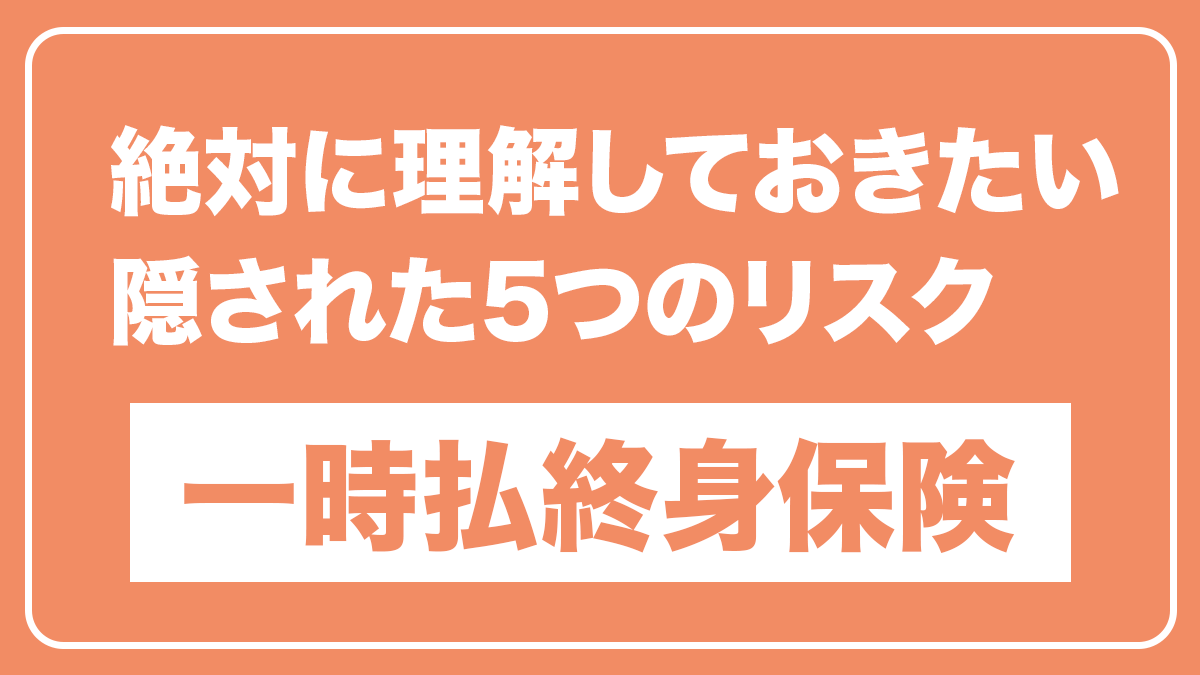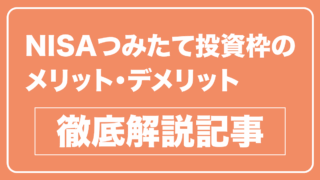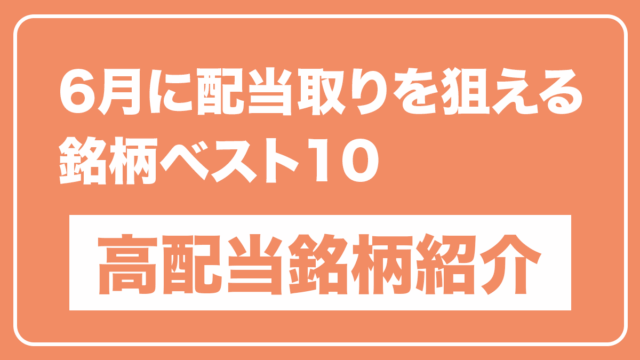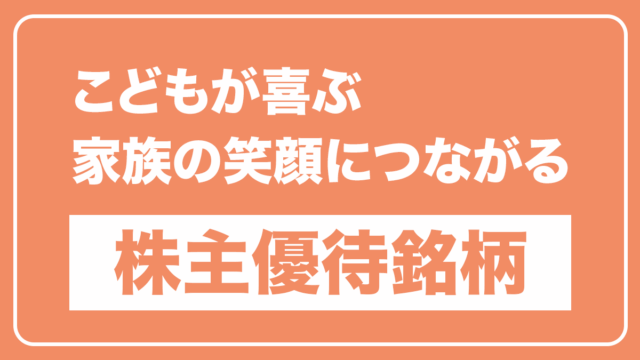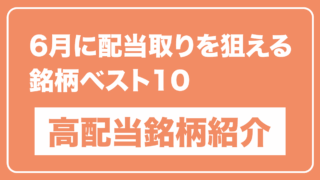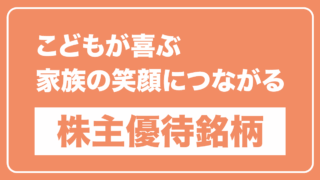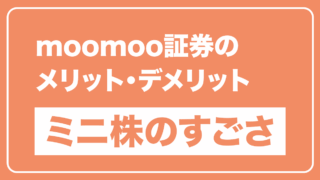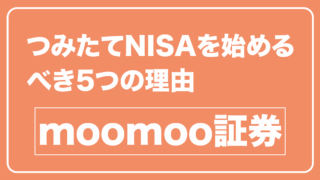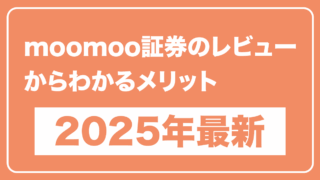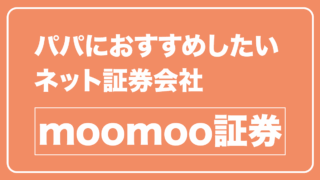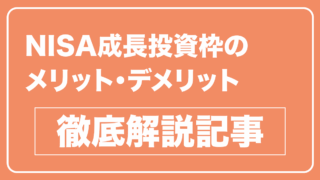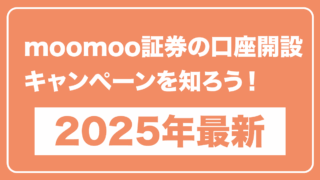銀行や保険ショップでよく耳にする一時払終身保険ってすごい良さそうだよね?
いや実は、気をつけないと痛い目に遭う可能性もある保険商品だよ
「預金より増えて投資より安全で死亡保障もつく」
確かに聞こえはいいですが、仕組みを知らずに飛びつくと家計に影響が出るケースもあります。
保険貧乏にならないためにも、加入は仕組みを理解してからにすべきです。
この記事では一時払終身保険について絶対に知っておくべきリスクを5つ紹介します。
特に、次のような方には役立つ内容となっています。
・すでに一時払終身保険に加入中の方
・深く考えずに一時払終身保険を検討している方
・一時払終身保険のリスクが全く分からない方

一時払終身保険のしくみを3ステップで理解
一時払終身保険は、名前のとおり「一度の支払い=一括払い」で一生涯の死亡保障を得る保険です。
人気の理由は死亡保証だけではなく「貯蓄性」がある貯蓄型保険だからです。
保障を得ながら貯蓄もできる保険で、満期時や解約時にお金が受け取れるのが魅力。
ステップ① 契約時に保険料を一括で支払う
まず契約時に保険料を一括で保険会社に支払います。
支払ったお金の中から保険会社は「販売手数料」と「かかった経費」を差し引き、残った金額を責任準備金として積み立てます。この責任準備金を原資に、よりお金を多く増やすために、保険会社は資産運用を行います。
保険会社は顧客からの保険料で株を買ったりするってこと?
そうだよ。「機関投資家」という言葉を聞いたことあるかな?企業や団体として投資活動を行う組織のこと。保険会社は機関投資家なんだ。
ステップ② 支払った保険料は保険会社の定める予定利率で運用される
一時払終身保険には「円建て商品」と、米ドルや豪ドルなどの外貨で運用する「外貨建て商品」があります。
また、死亡保険金額が「一定額を保障する商品」と「積立利率により変動する商品」の2つの一時払終身保険があります。
特に人気があるのが「外貨建ての変動型一時払終身保険」です。
保険会社が株式や債券などで資産運用して、運用実績によって将来受け取れる「死亡給付金額」と「解約返戻金」が変動するもの。
人気の理由は「予定金利の高いから」です。
日本円よりも金利が高い外国通貨で運用し、より高い利回りが目指せるとされています。
ステップ③ 死亡保険金もしくは解約返戻金を受け取る
実際にお金を受け取れるタイミングは
死亡した場合は、払った元本に運用益と“保障上乗せ分”が加算されて保険受取対象者(遺族)へ支払われます。
途中で解約した場合は、運用益から販売手数料などのコストを差し引いた解約返戻金が戻ります。
契約直後は手数料が大きいため返戻金が目減りし、年数が経つごとに少しずつ元本に近づいていく設計です。
まとめると、一括払い→保険会社が予定利率で運用→死亡時または解約時にお金を受け取るという流れです。
保険料一括払い
↓↓↓
保険会社が予定利率で運用
↓↓↓
死亡時または解約時にお金を受け取る
リスク① 早期解約による元本割れ
一時払終身保険は契約初期に高額な諸費用が差し引かれるため、契約直後に解約すると解約返戻金が払込保険料を大きく下回ります。
そのため、途中解約する可能性を踏まえた事前のプランニングが必要です。
特に子どものいる家庭では突然の出費があるので「一時払終身保険に加入しければお金があったのに…」とならないように本当に気をつけましょう。
もし一括払込保険料300万円支払って翌日解約したら?
- 一括払込保険料:300万円
- 契約翌日に解約 → 返戻金 約225万円
→結果は75万円マイナス(−25%)
(※低解約返戻金型の一時払終身保険の場合|目安)
リスク② インフレによる実質利回りの低下
例えば今後10年間、日本の物価が年2%で上がるケースを考えてみましょう。
固定予定利率1.25%の一時払終身保険(満期10年)を300万円一括支払いで加入したとします。
10年シミュレーション
| 項目 | 金額・指数 | メモ |
|---|---|---|
| 払込保険料 | 300万円 | 一括払い |
| 名目返戻金 | 340万円 | 1.25%複利×10年 |
| 物価指数 | 1.22 | 2%インフレを10年複利換算 |
| 実質価値 | 約279万円 | 340万円 ÷ 1.22 |
| 目減り幅 | ▲61万円 | 279万円 − 340万円 |
実質的な利回りはマイナス61万円もなってします。
予定利率は固定の場合、インフレ率が予定利率を上回る期間が長くなるほど「名目では増えても実質価値が減る」現象が起きます。
リスク③ 為替リスクを避けられない
これは外貨建ての保険全般に言えます。
外貨建ての一時払終身保険に加入するなら、為替は常に意識しないといけません。
外貨で運用されるため、円安が進めば利益が増え、円高になると元本割れのリスクが高まります。
外貨建ての場合:円高局面で受取額が目減りする
| 契約時 | 為替レート | ドル建て保険金※ | 円換算受取額 | 為替差による増減 |
| シナリオA (契約時) | 1ドル = 150円 | 20,000USD | 300万円 | 基準値 |
| シナリオB (解約時・円高) | 1ドル = 120円 | 20,000USD | 240万円 | ▲60万円(−20%) |
| シナリオC (解約時・円安) | 1ドル = 170円 | 20,000USD | 340万円 | +40万円(+13%) |
※払込保険料300万円を1ドル150円で換算すると20,000USD相当。運用収益・手数料は考慮せず為替影響のみを示しています
為替のインパクトは非常に大きいので現在(2025年6月時点)のような円安局面で一括払込みは損するリスクが高いですし、為替手数料も忘れてはいけません。
外貨建て保険は、保険料の支払時と保険金の受取時に円⇔外貨の両替が必要です。
この両替は保険会社が代行し、一般的に自分で両替するより高い手数料がかかるため、円換算の受取額を圧縮する要因となります。
リスク④ 解約返戻金に税金が発生する
解約返戻金が払い込んだ保険料を上回った場合、その差額は一時所得として所得税・住民税の対象になる点も注意が必要です。
解約返戻金の課税額は「差益−特別控除50万円の半額」で算出されます。
| 払込保険料 | 解約返戻金 | 差益 | 課税対象額 | 税額(所得税15%・住民税5%の場合) |
| 300万円 | 360万円 | 60万円 | (60−50)÷2=5万円 | 約1万円 |
※差益が50万円以内なら課税対象額はゼロです
もう一点注意が必要なのが「契約から5年以内に解約し差益が出る場合」と「契約者以外に解約返戻金が支払われる場合」です。
契約から5年以内に解約して利益が出た場合、雑所得として20.315%の源泉分離課税(所得税+復興税)が差し引かれます。
契約者以外(例:子や配偶者)が返戻金を受け取ると贈与税扱いとなり、金額が大きければ大きいほど税金は高くなります。
リスク⑤ 一括払いによるその他の投資機会損失
一時払終身保険のメリットは生涯に渡る死亡保障を手に入れられることですが、一方で「一気に現金がなくなり他の投資を検討できなくなること」のデメリットが大きいです。
結果、NISA・iDeCoなど税優遇付きの投資に資金を回せず、長期的な資産成長のチャンスを逃す可能性も。
想定年平均リターン5%のeMAXIS Slim 全世界株式(通称オルカン)に10年間で合計300万円をつみたてNISA枠内で運用した場合と比べてみましょう。(年間30万円×10年)
10年間の比較【つみたてNISA vs 一時払終身保険】
| 資金の使い方 | 最終評価額(概算) | 増減 | 備考 |
| 投資:つみたてNISA(年5%想定) | 約490万円 | +190万円 | 運用益非課税 |
| 一時払終身保険(予定利率1.25%) | 約340万円 | +40万円 | 死亡保障確保、運用益課税対象 |
→結果:つみたてNISAが 約87万円 上回る(為替変動・税金等を除く単純比較)
※20,000USD × 1.03¹⁰ ≒ 26,878USD。契約時と同じ 1ドル=150円で円換算すると約403万円
この表は為替変動なしのケース。為替が円高方向へ動くと、外貨建て保険の円換算価値はさらに低下して利回りも大きく減る可能性も考慮すべきです。
一時払終身保険「5つのリスク」と対策のまとめ
何も考えずに加入したら大変なことになりそう…
実際に保険の仕組みは分かりづらくできているから、「理解できないもの」には加入しないことが大事。まずは勉強しよう!
ここまで記事を読んでみると、一時払終身保険は「保障と投資をどちらも完璧にできる!」というような夢のような選択ではないことが分かったと思います。
一時払終身保険は一括払いで死亡保障と貯蓄性を得られますが
- 早期解約による元本割れ
- インフレによる実質利回りの低下
- 為替リスクを避けられない
- 解約返戻金に税金が発生する
- 一括払いによるその他の投資機会損失
子育て世代で一時払終身保険に加入する場合なら「満期まで解約しなくてもいい余裕資金があること」がマストだと思います。
資産形成を軸に考えるなら、つみたてNISAやiDecoで投資を行いましょう。